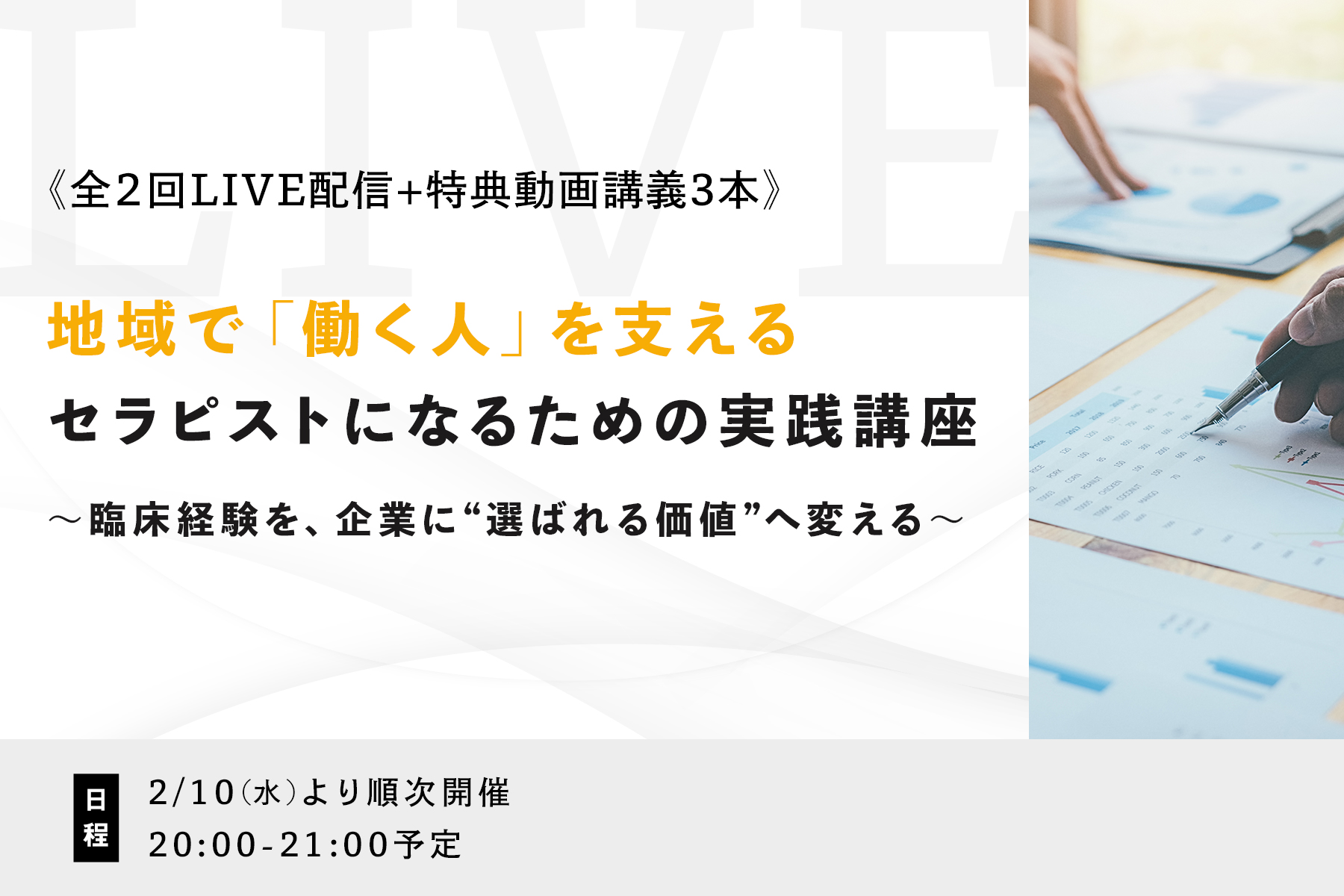緊急インタビュー 『世間から必要とされる現実的かつ着実なキャリアを考えたい』
2024年12月15日、22日、2025年1月12日、26日に、大規模作業療法フェス『リハキャリ2024』が開催されます。
このセミナーは、作業療法士が多く働く回復期リハビリテーション病院におけて働く上で必要なマインドや知識、技術、そして、そこから始まるキャリアについて、学び考えるためのセミナーです。決して、先人の成功を傍聴するそんな機会ではなく、『明日からの病院での働き方をアップデート』するためのセミナーです。
今回、3回に渡り、セミナー開催に先立ち、どうしてこういったセミナーを企画、開催することに至ったか、企画主である大阪公立大学の竹林先生 @takshi_77にお話を伺いました。
リハテックリンクス広報(以下、リ)「この度は、お時間いただき、ありがとうございます。早速ですが今回の企画をなさった意図を伺いっていきたいと思います」
竹林先生(以下、竹)「ありがとうございます。企画の意図ですね。わかりました。まずは、日本で作業療法士さんが最も働いている場所はどこかわかりますか?」
リ「どうでしょうか。私が学生の時は、とりあえず最初は病院と考えたことを覚えています。なので、やはり病院でしょうか?」
竹「そうですね。2021年の作業療法白書(https://www.jaot.or.jp/files/page/jimukyoku/OT_whitepaper2021.pdf)では、勤務している会員の約7割程度が身体障害に関連する病院で働いていると言われています(表1)」

リ「なるほど。やはり病院で働く作業療法士さんは多いのですね」
竹「そうなんです。ただ、最近の作業療法を取り巻く動きとしては、医療機関からより社会や地域へという流れが強くなっていると思います」
リ「どのような点からそういった思いを感じられますか?」
竹「基本的に、作業療法は障がいや疾患を有する方々に対して、提供されるものではなく、ヒト全体が対象とされています。したがって、疾患や障がいとともに生きておられる方がおられる医療機関だけでなく、より広範に社会と関わることが求められているんです」
リ「なるほど。では、今後も医療から地域へという流れは強くなってくるのでしょうか?」
竹「そうですね。日本作業療法士協会も色々な施策を作業療法5ヵ年計画という形で色々な策定を行ってきました。その中で、医療と介護の領域で働く作業療法士さんの割合は表2のような推移を辿ってきました」

リ「作業療法5ヵ年計画という言葉を初めて聞きました。日本作業療法士協会も職能団体として色々とやってきてくださってるんですね」
竹「知らない方も多いかもしれませんが、職能団体として、さまざまな施策が行われています。そして、日本作業療法協会の2023年から2027年の第四次作業療法5ヵ年戦略においても、上位目的として、【それぞれの地域ですべての人の活動・参加を支援する作業療法】をあげており、下位目的にも明確に【医療から介護保険・障害福祉制度・その他地域資源を利用した地域(在宅)移行支援のモデル提示と普及】という文言が明記されています(https://www.jaot.or.jp/files/page/somu/5years/kikanshi131-2023-2-15_kaisetu.pdf)」
リ「なるほど。そうなのですね。では、現場でもその動きは出てきているのでしょうか?」
竹「そうですね。明らかにここ数年の間に学会等で取り上げられるトピックスは地域と言いますか、医療以外の分野に関するものが増えたのではないでしょうか?」
リ「そうなのですね。では、例えばどのような領域が最近はトピックスとして取り上げられていますか?」
竹「代表的なものは、作業療法における自動車運転、学校作業療法、就労支援、産業領域、といったところでしょうか。従来の医療や介護といった公的保険下で行われていたフレームに加え、多くの作業療法士の働く場所が設立されてきたと感じます。これらの関しては、公的保険下の持ち出しによる拡張事業もありますが、別途公的予算、さらには起業や企業による自費等によるサービス提供等、雇用の形態のバリエーションも含めて拡大している印象を受けます」
リ「作業療法士が活躍できる場が増えたのは、とても喜ばしことですね」
竹「本当にその通りだと思います。社会に対して、作業療法が、作業療法士が良い影響を与えられる場所が増えれば、作業療法士の雇用の促進、さらには価値向上というところにつながりますので、重要なことだと思っています。実際、養成校で働いていて思うのは、作業療法士の求人は完全に売り手市場ですし、【雇用先がない】ということはありませんので」
リ「すごいですよね。では、今回どうして、注目されている【新しい働き方】ではなく従来の病院にフォーカスされたのですか?」
竹「そうですね。今、新しい領域で挑戦されている作業療法士の皆さんのほとんどが元々医療機関において、1対1で対象者の方に向き合っていた方がほとんどなのですね。実際、作業療法が生まれた場所であり、社会に浸透している米国の作業療法ですら、作業療法士の約半数が病院や作業療法オフィスで働いていると米国労働統計局の調査で言われています(https://www.bls.gov/ooh/healthcare/occupational-therapists.htm)」
リ「え?米国はもっと病院で働いている療法士が少ないのだと思っていました。」
竹「ですよね。僕も昔はそう思っていました。ただ、日本に比べると病院で働いている療法士の割合は2割近く低いという形でその差はまだ大きいですね。ただ、この割合を見ると、最近スポットが当てられている【新しい働き方】が、社会に対して影響力を持つ、貢献できる、という印象を持ちがちなのですね。でも、実際は、米国にせよ、日本にせよ、最も社会の仕組みの中において国家レベルで実装され、国民や社会に対して確実な貢献がなされている場の一つに病院という場所があると思うのです」
リ「灯台下暗しですよね。でも、確かに日本は、国民皆保険の影響もあり、病院がある、そして、医療を受けることができるのが、当たり前になりすぎていて、それ自体が社会貢献の一丁目一番地という事実に、国民も医療者も気づきにくいのかもしれませんね」
竹「だからこそ、多くの基盤となる病院での働き方、キャリアをやりがいや質の高いものに、そして充実させることが、作業療法の発展、敷いては日本国民に対する貢献につながると思うんです」
リ「なるほど」
竹「そして、やはり、病院という場所での働き方は、歴史があるものですから、新しく新鮮な景色は見えづらく、泥臭く、実直に、コツコツと積み重ねる必要があると思うのです」
リ「キラキラのキャリアのお話という感じではないということですか?」
竹「そうですね。その代わり、確実性が高く、さらには実現可能性も高いものだと思っています。大多数の方々が勤めておられる病院という場所だからできる実直なキャリア、そして、それに必要な知識や技術について、今回のセミナーでは学んできただきたいと思っています」
リ「今回、病院におけるキャリアに焦点を当てられた理由がよくわかりました。そろそろお時間ですね。それでは、次回はセミナーの具体的な内容について、教えていただきます。ありがとうございました」
竹「ありがとうございました」