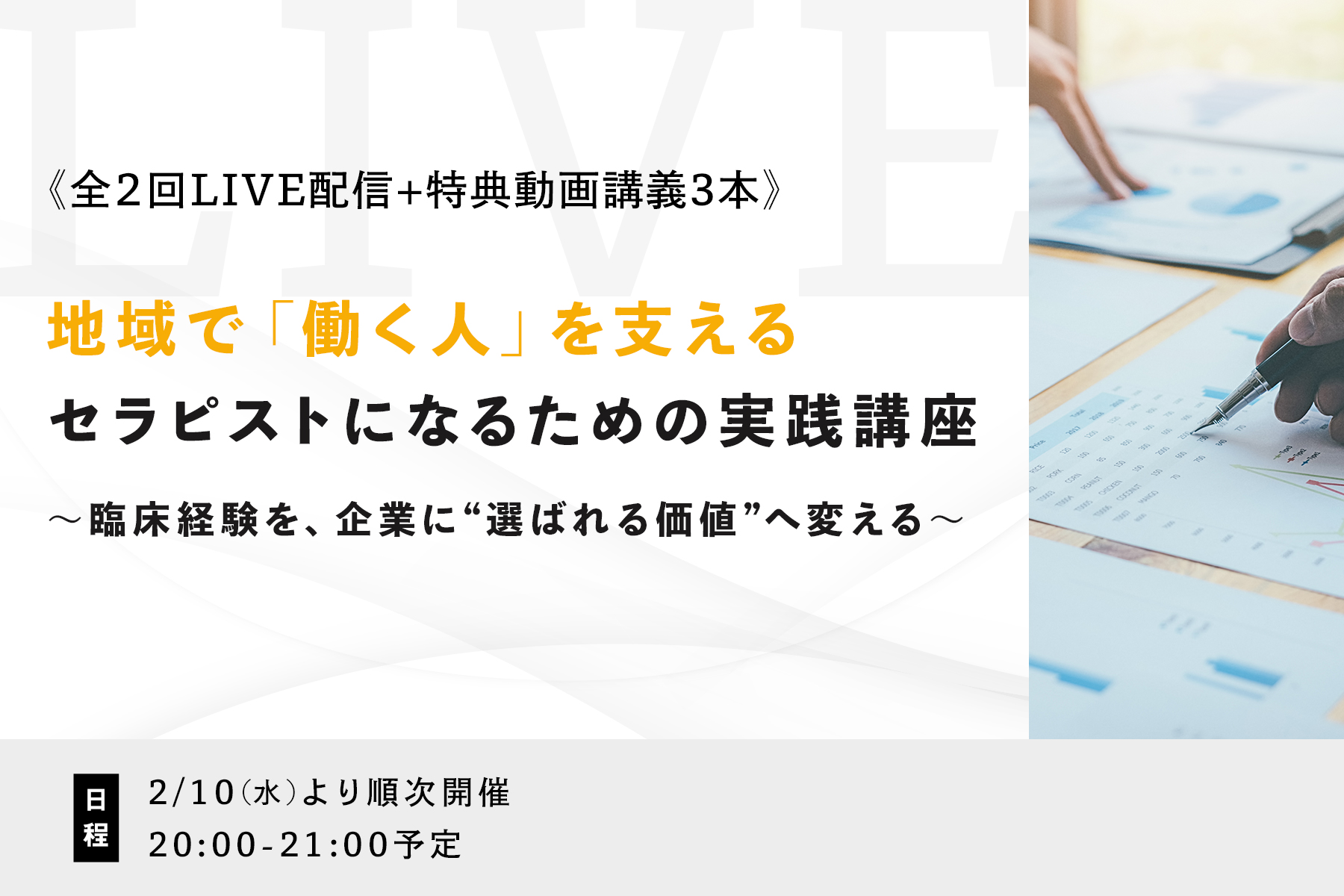緊急インタビュー 『病院における作業療法の価値とそれに必要な知識や技術』
2024年12月15日、22日、2025年1月12日、26日に、大規模作業療法フェス『リハキャリ2024』が開催されます。
このセミナーは、作業療法士が多く働く回復期リハビリテーション病院におけて働く上で必要なマインドや知識、技術、そして、そこから始まるキャリアについて、学び考えるためのセミナーです。決して、先人の成功を傍聴するそんな機会ではなく、『明日からの病院での働き方をアップデート』するためのセミナーです。
前回のインタビューではなぜ今病院に焦点を当てたセミナーを行うのかについてお話を伺いました。今回は、病院で働く価値やそれらに必要な知識について、リハキャリ2024の企画者である大阪公立大学の竹林先生 @takshi_77 にお話を聴いていこうと思います。
リハテックリンクス広報(以下、リ)「前回は、今、なぜ、病院のキャリアに焦点を当てるのかについて、お話を伺いました。領域が広がっていくのはとても好ましいである一方、基盤となる病院の作業療法士さんの働き方をさらに充実させることで、より社会貢献および職種の発展に繋がる可能性についてお話を伺いました。そこで、基盤という言葉ありましたが、この点について深掘りさせてください」
竹林教授(以下、竹)「ありがとうございます。これは自分が研究や医療機器および製品開発に携わる際、やはり臨床における対象者の方と向かい合い、そこで対象者の方と一緒に試行錯誤し、紡がれた【問題解決技法】が基盤になった、という経験があるからです」
リ「問題解決技法です?」
竹「そうです。問題解決技法です。自分が経験した中では、研究も医療機器も、商品の開発も【世の中のリアルの困りごと(問題)の解決】というニーズを満たすために行うものが多いのです」
リ「なるほど。つまり、世の中からニーズがないものを作っても仕方がないということでしょうか」
竹「仕方がないとは言わないですが、やはり、病院外でサービスを展開する際には、使ってもらえないと、廃れてしまい継続もできませんし、そもそも使われないサービスにどこまで社会的な意義があるかどうかは不透明な部分はありますよね」
リ「確かに。では、そういったニーズを感じれる場が臨床にはあるということですか?」
竹「そうですね。しかも、そのニーズを担当制の中で、一人の対象者さんにじっくり時間をかけて、試行錯誤することができる。そして、関係性を作りながら、その方々の想いや経験を鑑みた解決方法を考えていける、まさに作業療法に必要な関わりを、比較的時間をかけて積み重ねることができると思ってます」
リ「なるほど。でも、最近は働き方改革があったり、病院自体の勤務も周辺業務も含め、非常にお忙しいと聴いています。そういった状況の中で時間をかけて、作業療法に関する取り組みができるものなのでしょうか?」
竹「そうですね。病院自体は忙しいと思います。それは間違いありません。ただ、その上で、対象者の方に毎日2-3単位という時間の中で1対1で向き合える経験は、病院でなければなかなか確保できないのではないでしょうか」
リ「介護保険の領域でも週に関われる時間は毎日とはいきませんしね」
竹「そうですね。さらに、地域において新しく生まれた多くの領域では、1対1で関わるというよりも、組織や集団を対象とし、その中で各個人に対して素早くアセスメントし、組織と個人のそれぞれに利がある提案を瞬時に導き出すといった、メタ的な意識が必要な振る舞いが要求されることが多いように感じます。地域に出ると、作業療法士さんの数も限られますしね」
リ「それはかなり思考や行動のキャパシティやスピードが求められますね」
竹「そうですね。そして、個人的に何よりも重要だと思っているのは、一人一人の人生に対して深くアセスメントした経験数です。これらがあることで思考のバリエーションやスピードが大きく向上すると個人的には思っています」
リ「なるほど。きっちりと一人の方をアセスメントする経験を病院の中で積み重ねることによって、対象が集団や組織になった際にも、それらの集合知を元にアセスメントを行なっていくイメージですね」
竹「そうですね。そういう社会問題や人の人生そのものを学ぶことができる機会は病院という働く場所には無限に散りばめられていると思うのです。ですから、病院で働き続けるにしても、今後地域に出るとしても、眼前の対象者に対して作業療法を深めることができるという意味で病院が基盤にあると個人的には思っています」
リ「なるほど。対象者の方に時間をもって関われる知識、技術、そして経験を積むことで、マッサージや運動療法とは違う、本当の意味での作業療法を提供できることが重要なのですね。よくわかりました。では、次回のインタビューでは、病院での働き方を充実させるための要素について、セミナーの内容も含め、お伺いします。お時間いただき、ありがとうございました」
竹「こちらこそ、ありがとうございました」