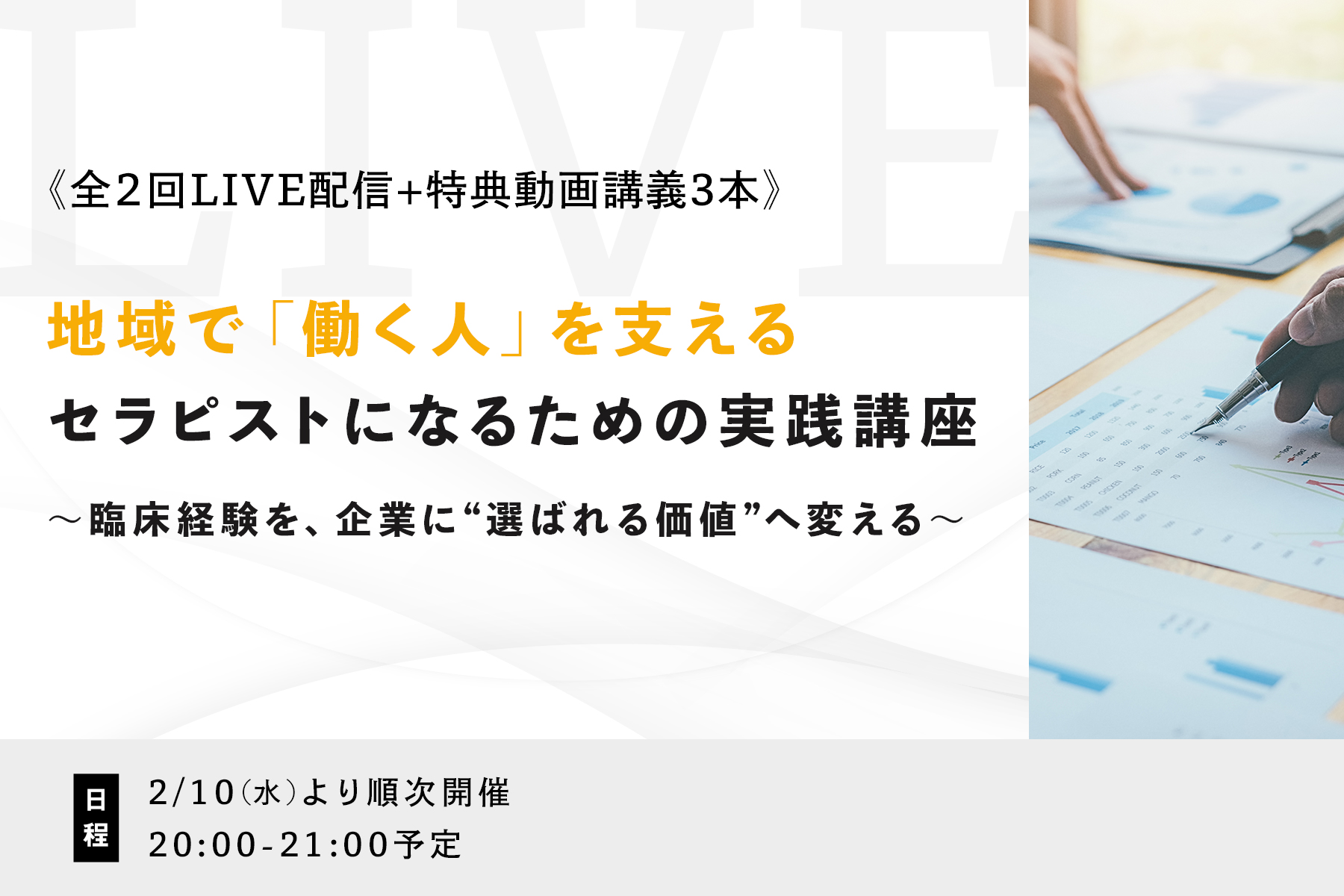リハキャリ2024 講義の感想と解説(1)「竹林先生、友利先生、講義まとめ」
皆さんこんにちは。12月15日のリハキャリ2024のDay1は楽しんでいただけましたでしょうか?第一線で実践されている多くの先生方に病院勤務からのキャリアパスに関するお話をいただきました
病院勤務からのキャリアパスというと「病院を辞めた後に役立つ、病院における経験」のように感じる方もおられるかもしれません。ただ、今回のDay1で語られた内容は、そういった未来に対する病院勤務の意味の話もありましたが、「病院勤務を充実させる、より深化させる」といったお話が多かったと思います
今回、リハキャリ2024のDay1の講義について、僭越ながら、リハテックリンクス中の人(作業療法士)が、簡単に解説を行わせていただきます。作業療法の経験は浅いですが、何卒よろしくお願い申し上げます。
第一回は8つの講義の2つ、大阪公立大学の竹林先生の「病院で作業療法士が働くことの社会的・個人的意味」と東京工科大学の友利先生の「OBPが切り開く、病院・地域・社会へのキャリアパス」について私の感じた見どころについて解説させていただきます。
『病院で作業療法士が働くことの社会的・個人的意味』
大阪公立大学 竹林崇先生
こちらの講義では、作業療法士の現状、今後の病院の立ち位置に関するお話を中心に展開されました。
日本の作業療法士が働いている場所について、日本作業療法協会が出版している作業療法白書によると会員数全体の70%が病院にて勤務しているとされています。日本作業療法協会は、病院と地域における作業療法士の割あうを50%ずつにできるように今まで多くの施策を組んできていますが、日本作業療法協会が行っている30年間の調査の中では変わらず、病院で働く療法士は70%前後で2023年まで推移しています。
これは日本作業療法協会の施策の問題というよりは、ここ2-30年の間に、回復期リハビリテーション病棟が全国的に整備されたこと、組織率が現在50%強である日本作業療法協会に入会する療法士が病院で働く療法士が多いという傾向によるものかもしれませんが、未だ病院で働く作業療法士が大多数を占めているのが現状です。
そういった中で、日本作業療法士協会は、第4次5ヵ年計画の中で、病院を含めて、地域により密着した作業療法の展開というものを主たる方針として打ち出しています。そういった流れの中で、病院の役割も、以前のように病院内で作業療法を提供するのみというわけには行かなくなっています。
というのも、病院勤務の療法士自体が通いの場や介護予防事業等の総合事業に参画しているケースが全国的にも増えてきている現状があります。つまり、病院もその背景にある医学的知識等を活かして、地域に関わることが求められています。
こういった背景のもと、病院における作業療法士の役割は院内におけるリハビリテーションの充実以外にも、介護保険事業、自費リハビリテーション、さらには、病院の知識に付帯する疾患特異的な地域サービスの展開(自動車運転支援、安全住宅への寄与等)が求められてきています。
すなわち、病院退職後に病院で学んだ医学的知識を活かす、という価値や意味のほかに、病院で働く作業療法士として、地域貢献を行なっていくという働き方が、社会的な意味を持つことになっていく可能性が高いです。
上記のようなお話の中で、病院における作業療法士の意味や価値に加え、今後必要とされる研鑽の内容や行動の内容について知ることができました。
『OBPが切り開く、病院・地域・社会へのキャリアパス』
東京工科大学 友利幸之介先生
こちらの講義では、日本独自の文化や日本国民の特徴を捉えて作成された日本作業療法士協会が打ち出している作業療法の定義について、そして、その作業療法が如何に国民の健康と幸福に寄与できるのかについて、定義策定に関わられた友利先生からお話がなされました。
1985年に定義された旧定義では「作業療法とは、身体障害又は精神に障害のある者、又はそれが予測される者に対し、その主体的な生活の獲得を図るため、諸機能の回復、維持及び開発を促す作業活動を用いて、治療、指導及び援助を行うことをいう」と定められています。ただし、作業という概念は、障がいや疾患の有無に関わらず、全てのヒトが共通して持ちうる者であり、その作業をアプローチの主幹として用いるのが我々作業療法士です。
そういった観点から2018年に定義の再検討が行われ、「作業療法は、人々の健康と幸福を促進するために、医療、保険、福祉、教育、職業などの領域で行われる、作業に焦点を当てた治療、指導、援助である。作業とは、対象となる人々にとって目的や価値をもつ生活行為を指す」という形で、障がいや疾患の観念に関係なく、対象を人々とし、さらに作業の定義についても触れられました。
策定の過程では、世界作業療法士連盟の定義がある中で、新たに定義を策定する意味があるのか等の議論もあったものの、日本の文化や日本人の特徴を加味したこれらの定義が完成したとのことでした。
こういった作業そのものの定義、そして、対象を作業療法士自身が明確に理解することで、どんな領域においても共通した作業療法の振る舞いが可能になり、病院、地域、社会に対して作業療法士にしかできない貢献があるということを学ぶことができました。
今回はリハキャリ2024のDay1の講座1, 2に関する感想でした。次回はDay1の講座3 北里大学の高橋香代子さんの「病院で充実して働くためのマインドセット」と生駒市立病院の石橋先生の「作業療法士の病院でのキャリア形成 −組織に貢献できる働き方−」についてまとめていきます。最後までご覧いただき、ありがとうございました。