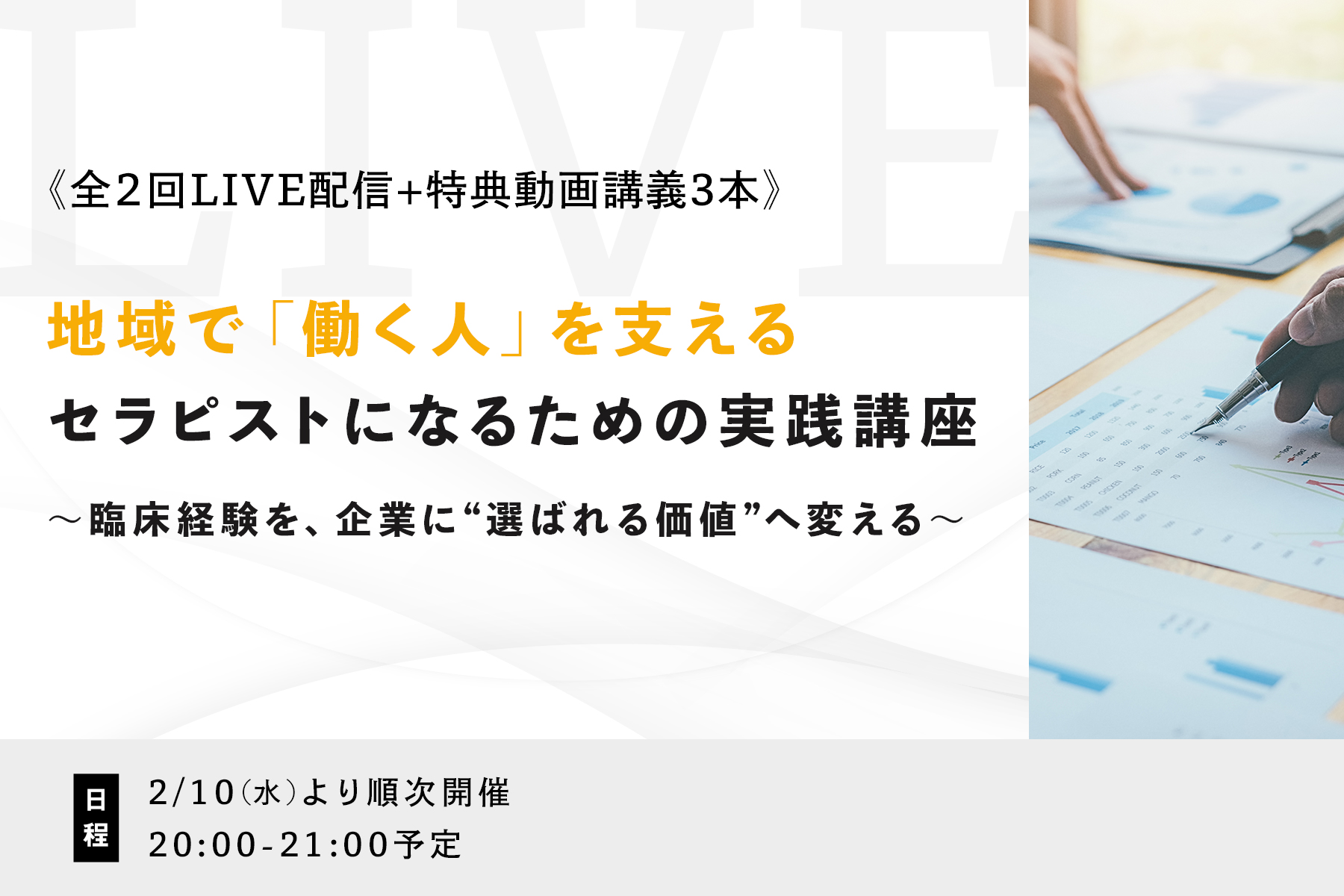リハキャリ2024 講義の感想と解説(2)「高橋先生、石橋先生まとめ」
皆さんこんにちは。12月15日のリハキャリ2024のDay1は楽しんでいただけましたでしょうか?第一線で実践されている多くの先生方に病院勤務からのキャリアパスに関するお話をいただきました
前回のまとめではDay1の講座1 大阪公立大学の竹林先生の「病院で作業療法士が働くことの社会的・個人的意味」と講座2 東京工科大学の友利先生の「OBPが切り開く、病院・地域・社会へのキャリアパス」について私の感じた見どころについて解説させていただきました
今回はDay1の講座3 北里大学の高橋香代子先生の「病院で充実して働くためのマインドセット」と生駒市立病院の石橋先生の「作業療法士の病院でのキャリア形成 −組織に貢献できる働き方−」について私の感じた見どころについてまとめていきます。
それではよろしくお願いします。
「病院で充実して働くためのマインドセット」
北里大学 高橋香代子先生
こちらの講義では、3つの軸を中心にお話がなされました。1つ目は、世界の作業療法士の働き方、特に米国、台湾における働き方について、2つ目は、日本作業療法士協会が支援するキャリアについて、最後3つ目は、病院で働く女性のキャリアの多様性についてです。
3つ目については、作業療法士の資格を有する方において、女性が非常に多いので、女性と名うちましたが、基本的には男性、女性同様に多様なキャリアを歩んで欲しいという想いのもとお話をされていました。
まずは世界の作業療法の中で日本は第二位の療法士数を誇っています。日本という国は比較的作業療法を受けやすい環境であることが言えると思います。ただし、米国の作業療法士と比べ、働く場所は圧倒的に病院が多いです。これは、学校等の福祉・教育領域において、社会が作業療法に求める事項の異なりもありますが、疾患を罹患してから、約半年間リハビリテーションを受けることができるといった社会保険制度の違いも大きく影響している可能性があるとのことでした。世界の作業療法において、病院で働くという選択肢は決して多くはない現状です。ただし、日本の医学モデルの作業療法に対するニーズや興味は高まっている現状もあり、多くの国から実習や見学の依頼もあるとのことでした。
次に日本作業療法協会のキャリア支援に目を向けると、やはり登録作業療法士(認定、専門)に関する制度の充実が挙げられます。日本作業療法協会においては、経験年数ごとの実践能力の目安を設け、基本的・標準的な作業療法の実践ができるように支援がなされています。これら、日本作業療法協会の教育制度の中で、自身のキャリア等に関する学びを得るのも一つの手段なのかもしれません、とのことでした。
最後、女性のキャリアについてのお話については、女性に限らず男性もプライベートでも、社会においても役割は刻一刻と変わっていきます。そういった中でライフワークバランスがとても重要になります。プライベートな生活の中でも、親になるなど、役割が変わる中でワークの部分の「やりがい」をより言語化する必要性が出てくると思うのです。
それを事例報告や日々言われて嬉しかったこと、実施して手応えを掴んだこと、それらをノートにまとめて、しっかり自分で認識しながら進むことで、やりがいを見失わずに過ごすことができると思います。これらを意識しながら仕事をすることが重要であるとお話をされていました。
「作業療法士の病院でのキャリア形成 −組織に貢献できる働き方−」
生駒市立病院 石橋ゆりえ先生
石橋先生のお話は、新人、中堅、そして、管理監督職として病院の中で貢献する上でも非常に参考になるお話でした。さて、石橋先生は冒頭で、「管理職になるぞ、と意気込んで働いてきたことはない。ただ、先輩や同僚の人たちに助けられ、ここまできたので、それらに恩返しをしたい、人の役に立てれば、という気持ちで働いてきた」ということでした。
こちらの講義では「組織における新人、中堅、役職者の立場での役割」と「組織における他者との関わり(同僚、上司、他部門に関して)」についてお話をいただきました。新人の頃は周囲のスタッフがすごく勉強熱心で、そういった方々とディスカッションを行う中で生じた疑問に対して一つ一つ勉強していくようなスタイルだったそうです。特に丁寧な新人指導というものはなくて『勉強は自分でするもの』という意識が自分の中ではありました。ただ、先輩方は質問をすると色々と話をしてくださり、その機会が自分にとっては良い指導になったということでした。
新人や若手がしっかり自主的に勉強している組織は組織として勢いがつく、そういった原動力のような役割が新人にはあると思います。雑務に追われて、そういった機会を失うことが組織の推進力を減衰させてしまう可能性もあるので、そういった点を管理等で配慮する必要性もあると思うとのことでした。
もう少し年代が進むと、外部、内部に対し、教育の機会も増えてきます。ただし、自分も研鑽の途中の中で教育をしていくのはとても葛藤を伴うものだったそうです。ただ、その中でもディスカッションやコミュニケーションの機会を多く持ちつつ、それらに注力をしていかれたそうです。
管理職になり、スタッフへの管理や教育等に携わる、他部署との折衝に関わる際でも、それらのコミュニケーションベースの関わりは変わらなかったそうです。特に、毎日、すべてのスタッフとなんでも良いので話すこと、他部署では少し難しそうだな、苦手そうだな、という職員の方から率先して、コミュニケーションをとることを意識されていたそうです。
石橋先生の話の中で、一貫して感じたことは、自己の動きがどう組織に影響を与えるのかを意識すること、そして、自己の動きを組織の力とするために、コミュニケーションという手法を利用されていたということでした。石橋先生のお話は働くということに少し悩みを抱えている、すべての療法士の方々に聞いていただきたいなと感じました。
今回はリハキャリ2024のDay1の講座3, 4に関する感想でした。次回はDay1の講座5 田中卓先生の「 」と6 伊丹脳神経外科病院の笹沼先生の「 」についてまとめていきます。最後までご覧いただき、ありがとうございました。