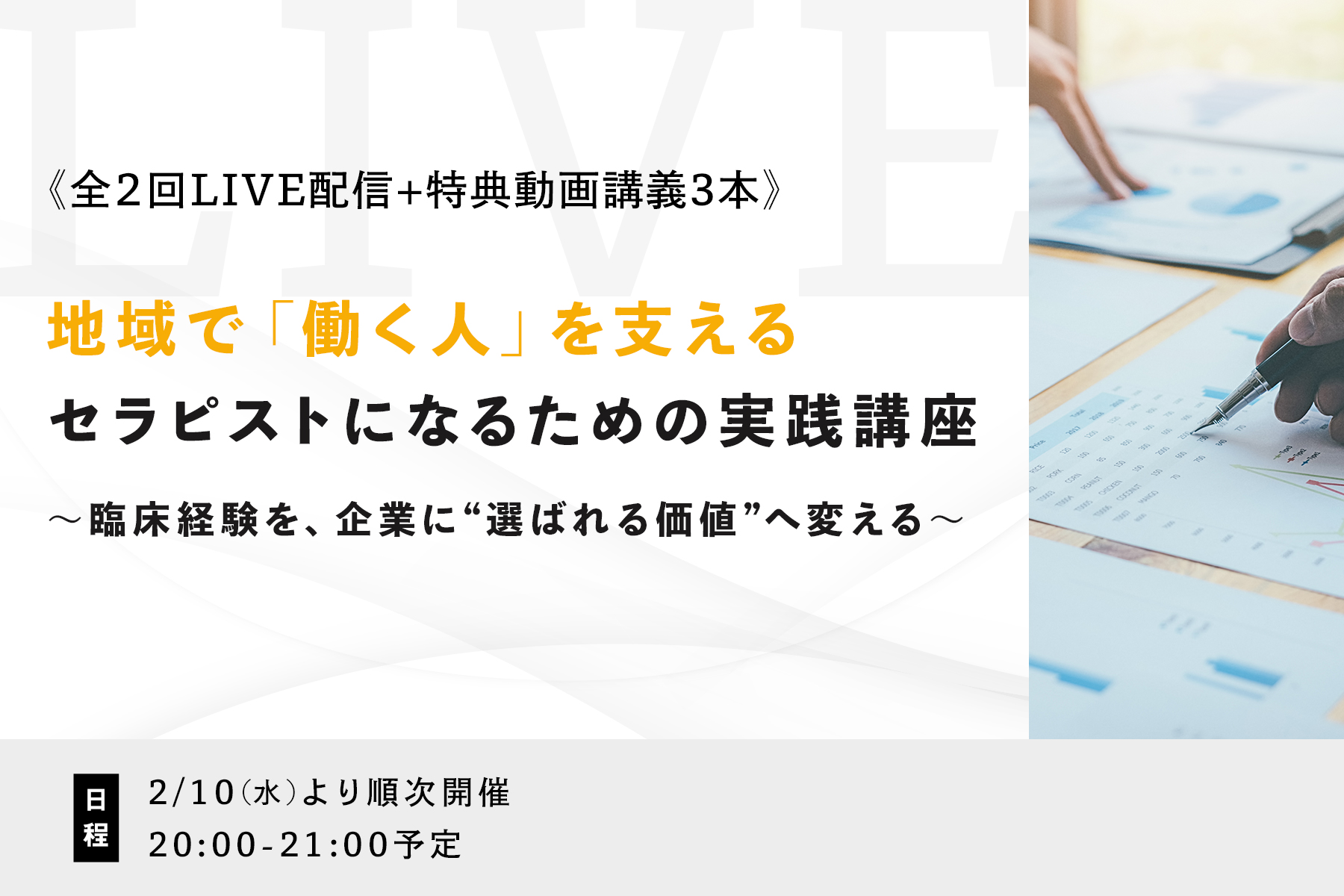リハキャリ2024 講義の感想と解説(3)「田中先生、笹沼先生、講義まとめ」
皆さんこんにちは。12月15日のリハキャリ2024のDay1は楽しんでいただけましたでしょうか?
さて、本日はDay1の第5・6講義についてまとめていきたいと思います。第6講義は養和病院の田中卓先生から「法人の中で働き方の幅を広げるために役立つスキルとマインドセット」について、第6講義については「訪問リハビリに活きる病院勤務経験」についてお話をいただきました。
田中先生は病院に所属しながら、法人内の働き方の幅を広げるための事業拡大という部分に関わっておられます。また、笹沼先生は病院内で働いた経験を活かしてできる訪問の取り組みについてお話をいただきました。では、詳細お話ししていきます。
「法人の中で働き方の幅を広げるために役立つスキルとマインドセット」
養和病院 田中卓先生
先生の所属される養和病院では次世代リーダー研修というものが催されており、職員が病院経営について知識を持つことで、自分ごととして病院勤務に従事できるように企画されているとのことでした。田中先生が今回プレゼンされていた『病院における自費リハ事業の新規創出』についてもその一環として実施されているそうです。
そもそも、養和病院はこれまでの運営の中でも、職員のアイディアから新規事業を立ち上げている実績があるそうです。例えば、メディカルフィットネスセンターでは、プロのサッカー選手、骨折、難病、脊損、脳卒中後の対象者の方、さらには、介護予防目的の方が、医療のマネジメント化で安全に運動を実施できることを目的に、職員の理学療法士の企画で始まり、実装された施設だそうです。
そういった風土の中、田中先生も次世代リーダー研修を通し、経営や企画に関する事柄を学び、自費リハの実装に貢献されたそうです(実際の、次世代リーダー研修に関しても、講義の中で触れてらっしゃいますので、ご興味のある方は今からでも、アーカイブをご覧になることができますので、下記リンクよりご登録くださいませ)。
経営に関して学ぶことで、新規事業の創出だけでなく、日々の臨床や組織のマネジメントに対しての考え方も変わるということです。日本には、通常の保険化の医療だけでなく、医療法人として地域貢献するために、いろいろな取り組みをされている病院があるのだなと感じました。また、自分がやりたいことをやるために起業という選択肢だけではなく、法人を巻き込んで取り組むといった新しいやり方だなとも感じました。
「訪問リハビリに活きる病院勤務経験」
伊丹恒生脳神経外科病院 笹沼里味先生
笹沼先生は大学病院にて臨床を開始され、その後、訪問事業に参画をなさったそうです。また、病院では脳卒中や整形といった一般的な疾患に加え、難病や内部障害等にも関わられることで、リスク管理をはじめとした医療的な知識を習得でき、それらが訪問リハビリの中で非常に活きているとのことでした。
訪問リハビリは、一人ひとりの人生をサポートする場であり、その中で対象者の方の「目標」を到達するために、最大限の(身体、精神)機能回復に加え、環境調整による代償的手段、行動変容プログラム等の全てを実施する必要があるそうです。
近年は、ひとりの対象者の方において、リハビリの対象となる疾患は一つではなく、多くの併存疾患を有する方が増えており、それらに対応するために、信頼される人間性と、スペシャリストかつジェネラリストといった高く、広い専門性が必要になるとお話しされていました。
また、訪問リハビリは対象者の方と、療法士が限られた空間の中で接するため、エビデンスを基盤としたリハビリテーションの提供が必要になり、さらには自宅環境においては、再発や突然死等のリスクも大きいことからそれらに対応できるスキルは必須になるということでした。病院だと、他の専門職がリスク管理に関わってくださるが訪問はそれらがないので、本当に気をつけないということでした。
また、訪問リハビリでは週に2日間、1日1時間程度しか介入ができないため、練習量といった点で大きな不足が生じます。したがって、訪問だからこそ、量を確保するための他職種連携が必要になるとのことでした。
講義の中では、訪問リハビリに必要な人間関係の作り方や、リスク管理をはじめとした医療的な知識を得るためにはどのようにすべきなのかについて具体的なお話をされていたのが印象的でした。
また、最後に対象者の方に、病院で得た医療的な知識や技術をどのように実際の対象者の方に提供したのかについて、具体的な事例を複数例示してくださいました(内部障害(呼吸器疾患)の対象者の方、脳卒中後に上肢麻痺を呈した対象者の方)。非常に具体的で勉強になる講義だったと思います。具体的な症例への介入等にご興味のある方は、今からでも、アーカイブをご覧になることができますので、下記リンクよりご登録くださいませ。
2つの講義について、いかがだったでしょうか。病院で働くことの意味について、非常に勉強になる講義だったと思います。是非、新人さんをはじめ、多くの作業療法士の方に聞いていただきたい講義だったと思います。