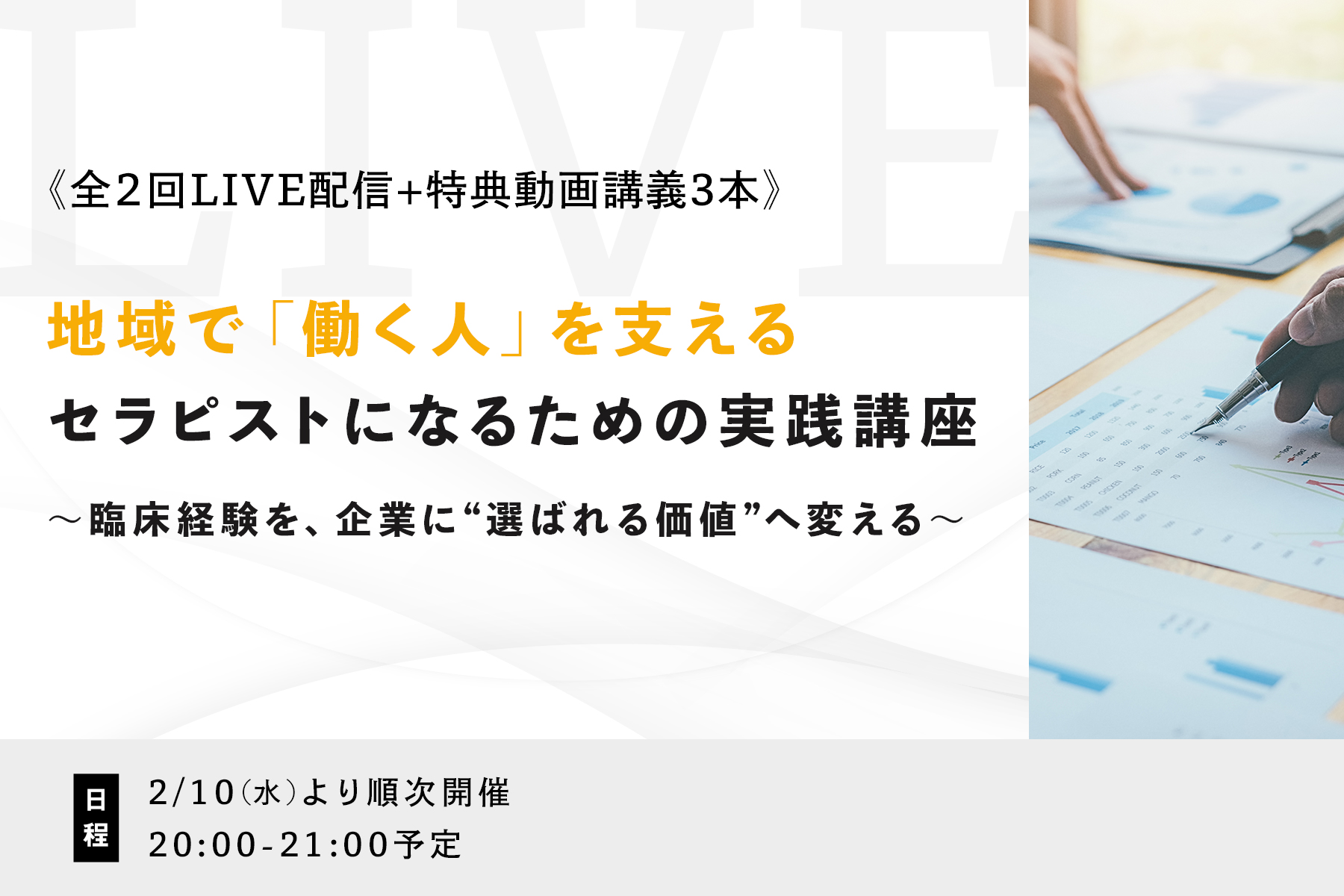リハキャリ2024 講義の感想と解説(9)
前回は、Day3 講義7 井野辺病院の加藤先生による『回復期における脳卒中の自動車運転』と 講義8 NPO法人日本学び協会ワンモアの金川先生『回復期リハ病棟などにおける就労支援の基礎知識』について感想を述べさせていただきました。
さて、今回はDay3最後の講義になります。Day3 講義9 農協共済中伊豆リハビリテーションセンターの生田淳一先生の「回復期リハにおける他職種で行う隊員支援に作業療法士がどのように関わるか?」です。
先にお示しした、加藤先生、金川先生のお話の延長になりますが、院内での支援をどのようにシームレスに地域に繋げるか、という部分が非常に重要だと感じています。それでは感想述べさせていただきますッ!それではよろしくお願い申し上げます。
「回復期リハにおける他職種で行う隊員支援に作業療法士がどのように関わるか?」
農協共済中伊豆リハビリテーションセンター 生田淳一先生
こちらの講義では、近年の「作業療法士は地域に出るべきだ」という風潮に対し、院内業務の繁忙の中、退院支援に関与する上で、必要な考え方や視点について、解説を行ってくださいました。
退院支援とは、退院に向けて生活全般を整えていく支援であり、退院間際に行うものだけではなく、入院直後から対象者やその家族とヒアリングを重ねる必要があり、その過程で、心身の機能、動作能力の改善と照らし合わせ、患者さんにとって理想の形を患者さんとともに共有していくもの、とお話しされていたのが印象的でした。
退院支援チームにおける作業療法士の役割としては、生活環境の調整、機能回復とそれらを生活に対し汎化すること、退院後の生活を見越したリハーサル(外出訓練、IADL訓練、退院前訪問指導等)、退院後の環境調整(住環境整備、患者・家族さんの指導、ケア会議等)が挙げられ、それらを遂行するために知っておきたい必要な基本的巡撫について、解説をくださいました。
また、その中でも取り立てて、退院前訪問指導、住宅環境の整備、患者・家族さんに対する指導ついて、詳細にお話をいただきました。退院時訪問指導の項目と検討すべき点の羅列、それらに関連する生活関連動作の評価、患者さんの価値観とのすり合わせ、具体的な施工例、さらにはコミュニケーションも含めた患者・家族さんへの指導について事例を上げつつお話しくださいました。特に、エビデンスを示しながら解説いただいた、患者・家族さん、そして療法士の3者で実施する介護指導、介護体験、に関しては、とても具体的で参考になりました。
最後に、退院時情報提供書を示す際の注意点、その際に知っておくと良い社会資源等についても共有いただきました。こちらについて、それぞれについて、さらに調べ、網羅的な知識を持って、患者さんの退院後の生活に有用な情報提供ができることが、退院後の生活にダイレクトに関わる重要な要因だなと感じました。
非常に、広い分野を網羅的かつ簡潔にわかりやすくお話しいただけたと感じました。退院支援は、地域での経験がなければ、難しいのかと感じていましたが、回復期リハビリテーション病院の中でもしっかり情報収集を行えば、多くのことが可能だということを感じました。特に新人さんをはじめとした、経験が浅い療法士さんには必見の講義だと思いました。
-------------------------------------------------
今回はDay3最後の講義になります。Day3 講義9 農協共済中伊豆リハビリテーションセンターの生田淳一先生の「回復期リハにおける他職種で行う隊員支援に作業療法士がどのように関わるか?」について、感想を述べさせていただきました。